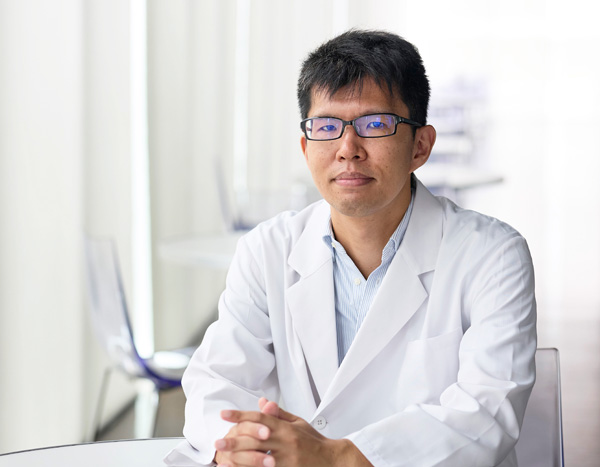
北岡さんは特定の菌にのみアプローチすることができる「バクテリオファージ」を使って肌荒れを防止する化粧水や、今後増えていくと予想されている薬の効きにくい感染症の薬の研究開発を行っています。
今回のインタビューでは、様々な応用ができるバクテリオファージを使って人や動物の悩みを解決する研究を進めている当センター利用者の北岡さんに、創業のきっかけや思いなどを伺いました。
株式会社DR.Phage 代表取締役 北岡一樹氏
~プロフィール~
2013年三重大学医学部卒業後、同大学医学部附属病院で研修を行ったのち、細菌学研究を志望し、名古屋大学大学院医学系研究科細菌学博士課程へ入学。様々な薬剤耐性菌の分子疫学研究に携わり、博士(医学)取得。培った細菌学研究のさらなる発展を求めて早稲田大学理工学術院で2018年から招聘研究員として研究を開始。同時に、医療法人社団予防会新宿サテライトクリニックで性感染症診療も開始し、2021年から院長を務めている。
社会実装を視野に入れ、臨床医学と基礎医学を繋ぐ、研究医かつ臨床医であることを目指し、現在は新規感染症治療法(ファージセラピー)実現の研究に注力している。
現在挑戦中クラウドファンディング:https://camp-fire.jp/projects/874417/idea
現在の事業内容について教えてください。
バクテリオファージを配合した肌荒れ防止の化粧水を製造販売しています。バクテリオファージは特定の菌に対して効果がある細菌で、色々な応用ができます。今回は黄色ブドウ球菌という多くの肌荒れの原因になっている悪玉菌にアプローチするファージを化粧水に配合することで、肌荒れの防止に効果がある製品を作りました。現在クラウドファンディングを使ってプレ販売を行っています。

いずれは薬が効かない耐性菌の感染症を治すために使う医薬品を開発したいのですが、まだ研究段階のため、まずは身近なトラブルである肌の悩みを解決することから着手しているところです。
創業しようと決めたきっかけは何ですか?
以前から薬剤耐性菌の研究をしていて、その過程でファージについても知りました。ファージは昔から研究されているのに、全然応用できていないと感じていて、自分の医者としての臨床的な知識を加えて、幅広く効くようなものを作りたいと研究を進めました。社会実装しようとすると、会社で研究開発するべきという風潮がありますが、新規性が強い事業内容であるため、既存の会社ではなかなか着手することが難しい。「であれば、自分たちで会社を作ろう」となったのがきっかけです。
当初は「ファージを使った物を販売する」くらいのビジョンでしたが、研究を進めるためには創業するしかなかったという事情があります。
創業する際に大変だったことは何ですか?
「創業のいろは」は全く知らなかったので、何もかもが大変でした。マーケティングも「D2C」という言葉すら知らず、製造販売許可の取得方法もわからず、いろいろな人にアドバイスを受けてなんとかしていました。
また、ディープテックとはいえ、化粧品レベルだと資金調達もなかなか難しく、融資に関してはセンターで相談に乗ってもらったおかげで得られたと思っています。
1人で始めたので人集めもとても苦労して、配信番組に出演したことがきっかけで今のチームを組むことができました。他にもモニターを行うことをアドバイスしてもらえるなど自分になかった意見を聞けたので、この出演がブレイクスルーになったのは間違いありません。
新宿区を事業拠点にしようと思ったのはなぜですか?
アクセスの利便性もありますが、住まいも職場も新宿区で、研究先も新宿区にあり、縁があったので「始めるなら新宿区かな」と思っていました。
新宿区で始めたことで新宿ビジネスプランコンテストに出場でき、入賞がきっかけで高田馬場創業支援センターを知り、入居することにしました。
今後の事業展開、ビジョンについて
今のところファージを使った4つの商品を1年ごとに出すということを考えています。化粧水の他に動物の肌の病気である膿皮症の対策、その次は性病防止のローション、そして虫歯を防止するファージくらいまでが描けています。ファージは応用しようと思えばいくらでもできるので、多くの人の意見を聞いて、困っていることに対応するファージの見つけやすさの組み合わせで、以降も製品を開発していきたいです。
新しい商品を開発するには、研究を加速させないといけないので、研究員を増やしたり、事務スタッフを増やしたりと、商品ができる毎に人を増やしていきたいと思っています。
創業を目指している方にメッセージをお願いします
ディープテックはどうしても結果が出るまでに時間がかかるので、資金的な体力やその過程を耐えられる精神力が必要になります。僕は思っていたよりも大変だったので、覚悟は必要だと思います。
しかし、研究者にとって、夢があるのも確かです。自分の研究のいきつく先が、社会にどんな効果をもたらすのか見てみたいと少しでも思うのであれば、起業は1つの選択肢になるのではないかと思います。まずは副業的に始めるのがいいかもしれません。